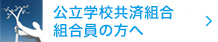無痛分娩について
- 2026年1月
- 公立学校共済組合中国中央病院
- 産婦人科
1.無痛分娩
当院では、無痛分娩という陣痛の痛みを和らげる方法を提供します。無痛分娩といっても、痛みが完全になくなるわけではありません。麻酔が分娩の進行の妨げとなったり、麻酔薬による合併症が出る可能性を減らすため、完全に痛みを取るのではなく、耐えられる痛みにコントロールすることを目指します。当院では、硬膜外麻酔という方法を用いて無痛分娩を行います。陣痛が来る前に入院して陣痛誘発を行う、計画分娩で行います。高度肥満などで医学的に困難と医師が判断した方以外、全ての希望する妊婦さんが対象です。
2.麻酔方法
硬膜外麻酔という無痛分娩において最も代表的な方法です。背中を丸めて横になっていただきます。背中を消毒し、細い針で局所麻酔を行います。背骨の隙間から針を挿入し、硬膜外腔というところに細いカテーテルを留置します。このカテーテルから麻酔薬を投与することで、痛みを和らげます。麻酔効果が不確実な場合は、このカテーテルを入れ替えることがあります。
3.実際の流れ
- 1)無痛分娩を希望される場合は、原則として妊娠36週頃までに同意書を担当医に提出してください。
- 2)妊娠36週頃に出血傾向がないか血液検査を行います。
- 3)妊娠37週以降の内診で、子宮口の状態をみながら担当医と入院日を決定します。
- 4)分娩当日は7時に入院し、必要があれば子宮口を拡張する処置を行います。
- 5)8時半頃から硬膜外カテーテルを留置し、その後、陣痛促進剤を開始します。
- 6)陣痛が始まり、痛みが強くなってきた時点で麻酔薬の投与を開始します。麻酔薬を注入してから陣痛の痛みが軽くなるまでに30分~1時間程度かかります。
進行が早い場合、十分に痛みが取れる前に分娩となることがあります。 - 7)安全のために、麻酔前からの絶食が必要です。当日は朝食抜きで入院していただき、分娩中も飲水のみになります。
- 8)麻酔が効いている間は足に力が入りにくくなることがあります。転倒などの危険を防止するために、無痛分娩中の歩行は控えてもらいます。トイレはベッドの上で行います。
- 9)産後2時間を目安に硬膜外カテーテルを抜去します。
- ※計画分娩日より前に陣痛が発来した場合は、無痛分娩は実施できません。
- ※陣痛誘発が不発であった場合は、後日改めて入院が必要になることがあります。
4.無痛分娩のメリット
- ・ 陣痛の軽減により、落ち着いて分娩に臨むことができます。
- ・ 分娩時のダメージが少なく、産後の回復が早くなることが多いです。
5.無痛分娩の合併症
医療行為は避けることができない合併症が起こりえます。当院では、スタッフ一同協力して診療につとめ、このようなことが起きた場合にも適切に迅速に対応できるよう準備しています。
- <ときに起こる合併症>
- ①血圧低下
麻酔の影響で一時的に妊婦さんの血圧が下がることがあります。点滴や薬を適切に使い対応することで、妊婦さんや赤ちゃんに問題がないようにしていきます。
- ②かゆみ
麻酔薬の影響で体にかゆみを生じることがあります。通常かゆみの程度は軽いですが、辛い場合は冷やしたりして対応します。
- ③発熱(20%)
硬膜外麻酔をした妊婦さんが38℃以上の発熱をする場合があります。発熱は分娩後に自然に解熱することがほとんどですが、発熱の原因を調べるために採血などの検査が必要となる場合があります。
- ④尿閉(1%)
排尿感が乏しくなったり、尿が出しにくくなることがあります。そのため尿道に細い管を入れて尿を出しますが、麻酔が効いているため痛くないことがほとんどです。
- <まれな合併症>
- ⑤頭痛(0.5%)
まれに硬膜外麻酔によって、分娩後に頭痛が起きることがあります。もし頭痛が起きた場合も1週間程度で落ち着いてきます。
- ⑥神経障害
まれに無痛分娩の後に足に痺れや感覚異常が起きることがあります。硬膜外麻酔だけでなく、分娩中の体位や分娩そのものも神経障害の原因となるため、注意深く診察させていただきます。大抵は数日で消失しますが、まれに数ヶ月から数年単位で持続することがあります。
- ⑦硬膜外血腫
極めてまれですが、カテーテルを挿入した神経の近くに血腫を作ることがあります。カテーテルを抜いた後に足の痛み、痺れの増強、足に力が入りにくいなどの症状があります。
- ⑧感染
極めてまれですが、カテーテルから細菌が入り感染を起こすことがあります。そのため髄膜炎や硬膜外膿瘍を来たすことがあります。滅菌された物品を適切に使用し、背中を十分に消毒することで予防に努めています。
- ⑨局所麻酔薬中毒
極めてまれですが、局所麻酔薬の濃度が上がりすぎたり、血管内に局所麻酔薬が入ることで起こります。唇や舌が痺れたり、痙攣、呼吸停止を起こすことがあります。
- ⑩高位・全脊髄くも膜下麻酔
極めてまれですが、麻酔が広がりすぎることがあります。分娩中に腕まで痺れたり、息が苦しくなった場合はすぐにスタッフにお知らせください。
6.麻酔の分娩への影響
計画分娩となるので、陣痛誘発が必要になります。一般的に無痛分娩では分娩の進行がゆっくりとなり、分娩時間が延長しやすくなります(特に初産の場合)。また、分娩時に鉗子分娩や吸引分娩が必要となる頻度が高くなります。帝王切開率への影響はありません。
麻酔薬そのものの影響や、母体の血圧低下により一時的に赤ちゃんの心拍数が下がることがあります。その他には赤ちゃんへの影響はありません。
7.無痛分娩が行えない方
- ・ 姿勢の保持ができない、高度肥満(BMI35以上)、脊椎の変形や手術歴があって穿刺困難な場合
- ・ 穿刺部位、全身の感染がある
- ・ 出血傾向(血小板数が10万未満)
- ・ 中枢神経系疾患
- ・ 重篤な心疾患
- ・ その他、医師が不適切と判断した場合
8.陣痛誘発について
安全に無痛分娩を行うために、陣痛誘発を行います。子宮頸管の熟化が不良の場合は、子宮口を開く処置を行います。陣痛促進剤であるオキシトシン製剤か、プロスタグランジン製剤の点滴を行います。
合併症として過強陣痛を起こすことがあり、非常に稀ですが子宮破裂を起こすと母児ともに命に関わることがあります。そうならないよう、陣痛促進剤を最初は少量から開始し、徐々に増量していきます。また、陣痛促進剤を使用している時は、分娩監視装置をつけて状態を観察します。産後に子宮収縮が不良で、多量に出血する弛緩出血を起こすことがあります。
9.費用について
自費診療となり、通常の分娩費用+約13万円となります。無痛分娩の麻酔手技を行った時点から費用が発生します。
途中で帝王切開に変更となった場合でも、無痛分娩費用は一律にかかります。